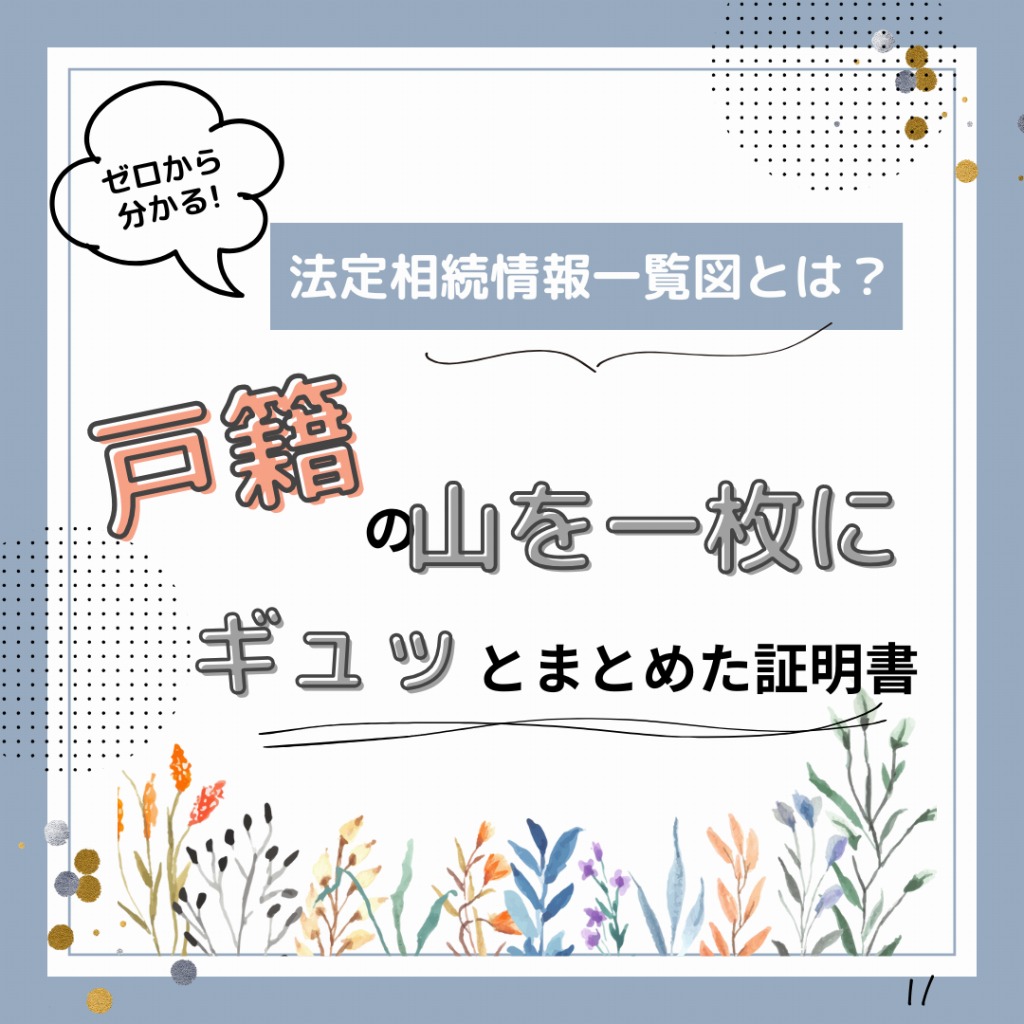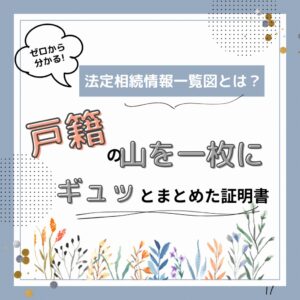~戸籍の山を、一枚にギュッとまとめた証明書~
身内が亡くなったあと、残されたご家族には、悲しみの中でもたくさんの手続きを進めなければなりません。
通帳を閉じる、不動産の名義を変える、年金や保険の届け出…どれも避けて通れないものです。
そんなとき、頼りになるのが「法定相続情報一覧図(ほうていそうぞくじょうほういちらんず)」です。
今回は、この聞き慣れないけれど便利な制度について、ご紹介します。
法定相続情報一覧図とは?
簡単に言うと、戸籍の束をぎゅっと1枚にまとめて、法務局が“公式に確認しましたよ”と太鼓判を押してくれる書類です。
「誰が相続人なのか」「どんな関係なのか」を図にしてわかりやすく整理し、法務局が内容をチェックして認証印をつけてくれます。
それがあるだけで、面倒な手続きをグッと減らすことができます。
どんな時に役立つの?
この一覧図は、相続にまつわるさまざまな場面で活躍します。
- 銀行やゆうちょ銀行の口座を閉じたいとき
- 土地や建物の名義を変更したいとき
- 株や投資信託などの証券関係の整理
- 税務署へ相続税の申告をするとき
- 年金関係の手続きなど
こういった手続きでは、通常なら「被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍」や「相続人全員の戸籍」を何通も何通も提出しなければなりません。
でも、この一覧図があれば、それだけで“相続人であること”を証明できるのです。
自分で作れるの?専門家じゃなくても平気?
ご安心ください。この一覧図は、ご自身でも作成できます。
必要書類は次のとおり↓↓
- 被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍
- 申出人(代表する人)の本人確認書類
- 一覧図の記載用紙(法務局のサイトでダウンロードできます)
※その他に追加で必要になる場合がある書類があります。
…とはいえ、戸籍の収集はなかなか骨が折れる作業。
昔の戸籍は手書きで読みにくいこともあり、時には“解読作業”のようになることも。
「ちょっと不安だな」と思った方は、行政書士・司法書士・弁護士などの専門家に相談するのも一つの手です。
申請は郵送でもOK。遠方の方にもやさしい制度です。
「法務局って遠いし…」という方も大丈夫。
一覧図の申請や交付は、郵送でのやりとりも可能です。
家にいながらにして書類を整えられる、まさに“今どき”の仕組みです。
法務局のホームページには記載例あり。手書きもOK!
一覧図の書式は、法務局の公式サイトからダウンロードできます。
記入例や提出書類の一覧も載っているので、初めての方でもチャレンジしやすいですよ。
「パソコンが苦手…」という方は、手書きでも問題ありません。
一覧図を作ると、どんな良いことがあるの?
メリット(いいところ)
✓ 戸籍の束を何度もコピー・提出しなくていい
✓ 何か所かで手続きを同時に進められる(銀行・法務局・税務署など)
✓ 認証された写しは、あとから追加でも発行してもらえる
✓ 作成・交付は無料(※戸籍の取得は別途費用がかかります)
デメリット(ちょっと注意なところ)
⚠️ 戸籍に間違いがあると受け取ってもらえない
⚠️ 作成には時間と手間がかかる(特に戸籍の収集)
⚠️ 一覧図そのものには「誰が何を相続するか」は書かれない
よくある勘違い:これは「遺産分け」の書類ではないので注意が必要です。
この一覧図は“誰が相続人か”を示すためのものです。
“誰が何を相続するか”――つまり遺産の分け方(遺産分割協議)までは関与しません。
たとえるなら、「メンバーリスト」はあっても「役割分担表」は別に作らないといけない、というイメージです。
まとめ ~相続の「道しるべ」に~
「法定相続情報一覧図」は、相続手続きの混乱を少しでもやわらげるための“道しるべ”のような存在です。
- 書類の整理を助け
- 各機関への説明をスムーズにし
- ご遺族のご負担を軽くしてくれる
そんな頼もしい制度です。
ご自身で作ることもできますし、心配な方は専門家にバトンタッチすることもできます。
まずは一覧図のことを知っておくことが、いざという時の安心につながります。
「今はまだ必要ないけど、いずれは…」と思われた方も、どうぞこの記事を手元に置いておいてくださいね。